若者に人気の町・幸福寺にある本屋さん「アロワナ書店」。地域密着型のこの書店で、三代目・ハッコウは名ばかりの店長となった。その頃、ハッコウのいとこの昼田は、六本木ヒルズのIT企業に勤めていた。店内でぶらぶらするだけのハッコウと、店から距離をおいて会社勤めをする昼田だったが、書店の危機に際し、二人でゆっくり立ち上がる。
『昼田とハッコウ』
著者:山崎ナオコーラ
定価:本体1,900円(税別)
若者に人気の町・幸福寺にある本屋さん「アロワナ書店」。地域密着型のこの書店で、三代目・ハッコウは名ばかりの店長となった。その頃、ハッコウのいとこの昼田は、六本木ヒルズのIT企業に勤めていた。店内でぶらぶらするだけのハッコウと、店から距離をおいて会社勤めをする昼田だったが、書店の危機に際し、二人でゆっくり立ち上がる。
『昼田とハッコウ』
著者:山崎ナオコーラ
定価:本体1,900円(税別)
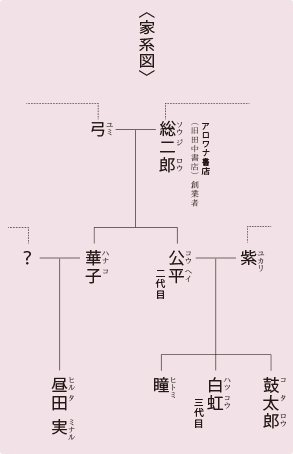
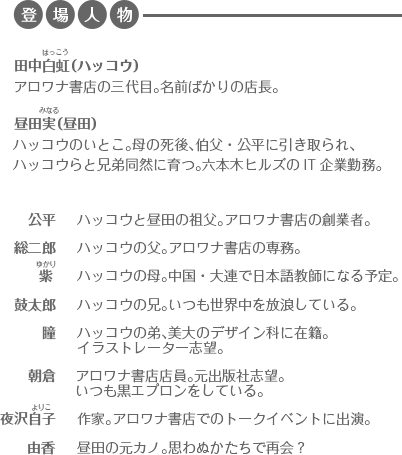
お父さんはとんかつとビール、お母さんは五目そば、子どもたちはもちろんお子様ランチ。一つの大きな食堂で和食、中華、洋食と何でも頼めた。それぞれの専門店に行けば、もっとうまいものが食べられるのかもしれないが、家族全員がそれぞれ食べたいものを同時に頼めるのはその手の場所しかなかった。いまならフードコートかレストラン街になるのだろう。いずれにしてもそれは専門店の集まりだ。
町なかに昔からある本屋はちょっとお好み食堂に似ていないだろうか。その店には家族のだれが来ても何かしら買うものがある。でも同時に物足りなさを感じることもあるかも知れない。品揃えには限りがあるから。だから本屋は進化した。お好み食堂がフードコートになったように、本屋は専門書店の集まりみたいに大きくなった。さらにいまは中古品を幅広く集めた安売り店もあれば、ネットでどんな本でも注文できる本屋もある。買う側、読む側にとって利便性が上がるなかで、それでも変わらずに人々が町の本屋に求めることがあるとしたら、それは何だろう。
後継ぎとなったハッコウにも、六本木のIT企業を辞めて店を手伝うことになった昼田にもそれはまだはっきりとは分からないようだ。
一見ふまじめでいい加減、怠け者なのに女性にも子どもにもなぜかもてるハッコウ、自分のやりたいことは二の次で世の中での自分の役割は何なのかに心を常に砕いてきた昼田。二人ともが選んだ町の本屋というかたちに、未来につながる方法が隠されていないだろうか。若い二人にとって、本屋は懐かしむべきものではないはずだ。大型店もチェーン店もネット書店もそれぞれの進化を遂げる。アロワナ書店も、本質を見極め未来を見据えた試みを行いながら、一方で日常の仕事も手を抜かない。二人ならばきっとうまくやるだろう。
笈入建志(おいり・けんじ)
一九七〇年生まれ。大学卒業後、東京旭屋書店に入社。六年間の勤務を経て、現在、東京・千駄木の「町の本屋」往来堂書店店長。
小さな頃から、「作家になりたい」と私は思ってきたのですが、そのイメージは、書店の平台でした。あるいは、棚にささっているのでも良いのですが、とにかく、自分の書いた文章が、活字になって、書籍になって、書店に置かれる、それが夢でした。中学生、高校生の頃は、書店の中を毎日ぶらぶらしていました。ですから、初めて書店の平台で自分の考えた言葉(タイトルやペンネーム)を見たときは、その場で本当にだらだらと涙が出ました。POPが付いているのを見つけ、さらに泣いてしまいました。今でも、泣くほどではないにしろ、自分の書いた本を書店で見ると、手がびりびりします。「夢の実現」を目の当たりにしている感覚があるのです。
単行本を出版すると、通称「書店まわり」と呼ばれる、書店さんに「この本をよろしくお願いします」と挨拶する販売促進活動を行います。いろいろな作家がいますし、この活動をしないという考えの方もいらっしゃると思うのですが、私は最初に「書店まわり」をしたときにものすごく楽しさを覚えまして、販促効果のほどはわからなくても作家として勉強になるから許されるならできるだけ行きたいと思い、以降、どの単行本出版の際も、少なくて三日、多くて一週間かけて、都内の書店さんに挨拶まわりをするようになりました。時には、編集者さんとご一緒せず、自分ひとりだけで行かせてもらうこともあります。大阪や京都、福岡の書店などを、自腹でひとりでまわったこともあります。忙しい書店業務の中に割り込んで挨拶するので恐縮なのですが、私はとても楽しく、勉強になります。
最近になって、いわゆる「書店」というものがなくなるという噂が流れ始めました。ネット書店、新古書店、チェーン店の新しい広がり、いろいろな形態の店が生まれるようになりました。書店は今、新しい形に変化しようとしています。電子書籍の台頭で、紙の本がどうなっていくのか、なくなるのではないかという不安も聞きます。私は古いものに拘泥しようとは思いませんが、新しいものだけに価値があるとも考えません。
こういったことから、書店にとても思い入れがあります。
ただ、ここまで書いておいてなんなのですが、『昼田とハッコウ』は初め、書店を舞台には設定しておりませんでした。
まず、「小規模な店を舞台にしたい」「″街”を書きたい」という思いがありました。
当初は蕎麦屋を舞台にと考えておりまして、実際に蕎麦屋さんに取材もさせていただきました。ただ、自分が好きで数年前まで通っていて、「この人に話を聞きたいな」と考えていた蕎麦屋さんがあって、そこへ行こうとしたらその店は潰れてしまっていて、当時の店主の方は現在、違う仕事をされていることがわかりました。それがショックで、意気消沈してしまいました。
どうしよう、と考え込みまして、本当は、自分自身の職業からは遠い話の方が良いのだろうけれども、やはり得意分野でいくか、と書店に方向転換しました。
まず、なぜ書店の仕事について物語構築に不必要なほど書き込みたいと考えたかを申します。「書店」という概念が十年後には残っていないかもしれない、という書店文化末期の時代に『昼田とハッコウ』を出版することになると考えたからです。そうしますと、「書店」というものがどういうものだったかを書き残すということに、良くも悪くも意味が出ます。いわゆる「良い小説」にしよう、完成度の高い物語を構築しよう、と考えた場合には、仕事の記録、流通の説明、といった部分は除くべきでしょう。しかし、私は、「良い小説」でなくていい、完成度も高くなくていい、と思いました。賞をいただかなくても、読者がページを捲ってくれさえすれば、小説はパワーを持てます。
単純に書店文化がどういうものだったかを記録する文章を織り交ぜながら、且つ次のページを読みたくなるようなリズムを作り、編み上げました。
しかしながら、現実の書店員さんが御覧になったら、「いや、本当の仕事はこんなのと違う」と思われる箇所もあるかもしれません。ただ、私としては、リアリティを出そう、という意識は確かにありました。
それで、「書店まわり」で知り合った書店さんにお願いして、バックヤードを取材させていただいたり、書店員さんに話を聞いたりしました。
それから、もともと「書店まわり」で得ていた知識や感覚も使ったかもしれません。
また、もう十年以上も前になりますが、私には書店でのアルバイト経験がありますので、それが活きている箇所もあるかもしれません。
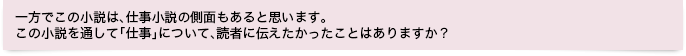
伝えたいことはありません。
小説は、伝えたいことを核にして作るものではない、と考えています。
よく、このような、「伝えたいことは?」「メッセージは?」といったご質問をいただくのですが、もし何かを伝えるために生きているとしたら、小説ではなく、論文を書きます。
仕事をしたり、恋をしたり、ということが人生には起こりますが、それらの神髄を知りたかったら、実際に仕事や恋をするのが一番に決まっています。小説を読んでも仕方がありません。
「仕事小説」「恋愛小説」とは何か? に迫る方が面白いと思います。
小説はツールではありません。小説そのものが目的なのです。
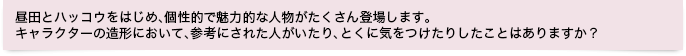
九年前に、文藝賞という新人賞を「人のセックスを笑うな」という作品で受賞して、私は作家活動を始めたのですが、それは私が文藝賞というものにチャレンジした三度目のことでした。前年は、「鼻血の神様」(一次審査止まり)、前々年は、「タナカハッコウ、終わりの旅」(二次審査止まり)、という作品を送っていました。ですので、私にとって小説というものを書いたのは、「タナカハッコウ、終わりの旅」が初めてになります。私は幼稚園の頃から作家を目指していたのですが、「社会人を三年ほど経験してからなるものだ」という思い込みがあって、高校生になっても短編小説すら書きませんでした。しかし、大学四年生のときに、卒業論文を書いてみたら、規定の五十枚が書けたので、「だったら、文藝賞の規定の百枚の文章も書けるかもしれない」と思い、小説を書いてみました。この「タナカハッコウ、終わりの旅」は、『昼田とハッコウ』とは似ても似つかない、「男子高校生二人が熱海へ卒業旅行に行く」というだけの話であり、ストーリーで『昼田とハッコウ』にかぶるところは全くないのですが、ハッコウという名前と、男の子二人、というイメージだけは同じです。「冷徹で有能なのに謙虚な男の子」と「何もできないのに尊大な男の子」の組み合わせですね。一種の「萌え」ですかね。
それと、一人称小説の面白さとして、語り手と主人公を別にする、ということがありますよね。その面白さを楽しみたい、という気持ちもありました。
登場人物に関しては、そういうところを大事にして書きたいと思っていました。ただ、現在の私は三十四歳になっておりまして(『昼田とハッコウ』執筆時はもう少し若かったですが)、「男の子を書く」「かっこよさを出す」「若者の感覚を文体に活かす」という力は、この先は衰える方向に進んでいくと覚悟しています。ですので、今後は、このセンスを活かして書く、ということは一切止めようと考えております(『昼田とハッコウ』の販促フリーペーパーで言うことではないので細かくは言いませんが、これからは違う努力をしていきます)。今後は、小説に若者を登場させるとしても、若者言葉や若者センスを大事にするようには書きません。
『昼田とハッコウ』を、若者言葉で書く最後の作品にします。
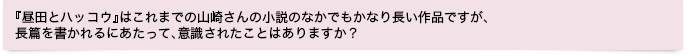
「日常淡々系」と呼ばれるジャンルがあります。正式な名称ではありませんが、「なんとなく、ああいう作品の系列かな?」と思い浮かぶ人は多いと思います。
日々のことを描くことで、「戦争反対」という言葉を使わずに、戦争に反対することができるようなジャンル、と私は捉えています。
ここで、柴崎友香さんの『青空感傷ツアー』(河出文庫)の、長嶋有さんによる解説から、一部分を書き写させていただきます。
柴崎友香さんや長嶋有さんの作風は、私の書くものとは違うので、一緒に論じると嫌がられるかもしれません。
ただ、私はこの解説に深い感銘を受けましたし、「読み応えがなければ、長いものを読む意味がない」と思われる読者に、何かのとっかかりになるかと思いましたので、ここに引用させていただきました。また、この文庫は二〇〇五年十一月に刊行されたもののようですから、9・11という言葉が取り上げられていますが、現在だったら、おそらく3・11のことをお書きになると思います。
『昼田とハッコウ』は、二年間の連載期間において、リアルタイムで執筆しました。現実世界のひと月遅れの設定で、その月のことを発表する、という手法です。
そのため、3・11のことに触れないのはおかしいことになるので、さらりと触れました。しかし、小説ですので、私の考えを書くことはしませんでした。
とばし読みでいいですよー。
小説に向かうときって、国語の授業のように一文一文解釈するとか、作者の意図を汲むとか、真面目にしてしまいがちかもしれませんが、授業ではないときの読書時間は、自分だけのものです。自由に読んでいいんです。不真面目でいいんですよ。一行飛ばしでも、最初と最後だけパッと読んでも、何年かおきにページを開いてもいいんです。
ちゃんと読んでいないまま、勝手な意見を言ってもいいんですよ。
山崎ナオコーラ(やまざき・なおこーら)
1978年生まれ。幼い頃から書店に通い、平台に自分の書いた小説の本が積まれることが夢となる。大学四年の就職活動の時期に初めて小説を書き、新人賞に応募した。二回の落選を経験し、三年目、会社員をしながら書いた「人のセックスを笑うな」で、2004年にデビュー。著書に、『カツラ美容室別室』『論理と感性は相反しない』『長い終わりが始まる』『この世は二人組ではできあがらない』『ニキの屈辱』などがある。
目標は、「誰にでもわかる言葉で、誰にも書けない文章を書きたい」。
グーテンベルク以来の出版業界の激変の中、書店文化をどう残していくか、日々考えている。