
──血の繋がりはなく、肉体関係もないにもかかわらず、ひとつ屋根の下、身を寄せ合い生きる芳子と周也。恋愛を超えた女の業が描かれた『雨心中』が文庫化となりました。
普通の男女の恋愛ものではなく、どこか歪んだ関係を書きたいと考えてこうした設定になったのですが、講談社で書くのは初めてだったこともあって、凄く緊張していた記憶があります(笑)。
──その二人の関係性ですが、これほどの芳子の執着を理解できない、もっという「気持ち悪い」と感じる読者もいるかもしれません。
その気持ちは理解できます。だけど「気持ち悪い」と思うのは、自分のなかにそういう感情があることを分かっているからじゃないかな。女は狙った男によって自分の顔を変えていくことくらい、普通の恋愛から学んでますよね。本当は嫌いでも好きな顔はできるし、好きだという気持ちを抑えることもできる。芳子にとって周也は恋愛対象だけど、周也がそれを望んでいないことも彼女は分かっているんです。 芳子は決してただ純粋に周也に尽くしている、貞淑な女というわけではないんですよ。周也も考えたらずで愚かな男の子だけど、芳子も心のなかにどろどろとした屈託を抱えている。でも自分のそうした部分を、薄々気付いてはいても認めたくないんですね。認めたくないから周也を守ろうとすることで、プラスマイナスゼロにしたいと思ってる。自分の危うさを自覚したくなくて逃げている部分があるんです。
──ある意味、これまでの唯川作品の中で一番複雑なヒロインかもしれません。
話のなかで芳子が繰り返し自分でも口にしているけど、周也をこんなにダメにしたのも芳子だし、追い込んでいるのも芳子。挙句、甘やかされ続けた周也がなんども問題を起こして追われる身になってしまう。芳子はどこまでも「一緒に行く」というけど、裏を返せば芳子が周也を連れて行っているともいえる。なのに本人はその自覚がない。多くを望んでいるつもりもないし、周也を守っているつもりだけど、実はとても欲深くて、怖い女なんですよ彼女は(笑)。
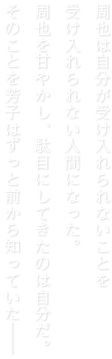
──唯川さん自身は芳子が抱いている「所有欲」、あるいは「執着」という感情について、どう捉えていらっしゃるのでしょう。
恋愛に関して言えば、若い頃は相手の男性について、そりゃあ執着はありましたよ。でも基本的には一時のものだと思っています。恋愛ってどうしてもちょっと頭がおかしくなる部分があるでしょう(笑)。だけど、今振り返ると、本当にその人が必要で執着しているとは限らないんですよ。「執着する」っていう病にかかっているような状況も多い。そうした意味で、周也に執着し続ける芳子は、特異な人間だと思うのですが、でも、そうとしか生きられない彼女の業のようなものを描きたかった。
──2014年には、デビュー三十周年を迎えられます。「これから」については、今どう考えていらっしゃいますか。

少女小説を書いていた頃から、もうダメかもしれないという不安はずっとあったし、今も葛藤がなくなったわけじゃありません。年数を重ねればスラスラ書けるようになると思っていたけど、全然そうならないことに自分でもビックリしています。でも、それが一冊の本になると嬉しいし、自分が思うようなものを書けたときの興奮も忘れられないんですよね。 これからは、たとえば「なにか恋愛小説を読みたいな」というときに選んでもらえるだけじゃなくて「唯川恵を読みたい」と思って頂けて、さらに興味を持ってくれた読者に「こんな唯川恵もいるのか」と作品ごとに驚いてもらえるようになれたら嬉しい。そうなりたいと思っているし「また別の唯川恵を見たい」と言われるようにもなりたいですね。そのためには、これからもコツコツ努力して、まだまだ少しずつでも上手くなっていきたい。三十年経っても上手くなる余地がある、ということを、自分でも期待しています(笑)。
![]()
1955年、石川県生まれ。金沢女子短期大学卒業。銀行勤務を経て、1984年「海色の午後」で第3回コバルト・ノベル大賞を受賞して作家デビュー。2001年『肩ごしの恋人』で第126回直木賞を、2008年『愛に似たもの』で第21回柴田錬三郎賞を受賞。
著書は『ベター・ハーフ』『めまい』『ため息の時間』『一瞬でいい』『とける、とろける』『天に堕ちる』『セシルのもくろみ』『ヴァニティ』など多数。最新作に『手のひらの砂漠』(集英社)がある。